俳句の歴史は?上手な俳句の作り方とは?
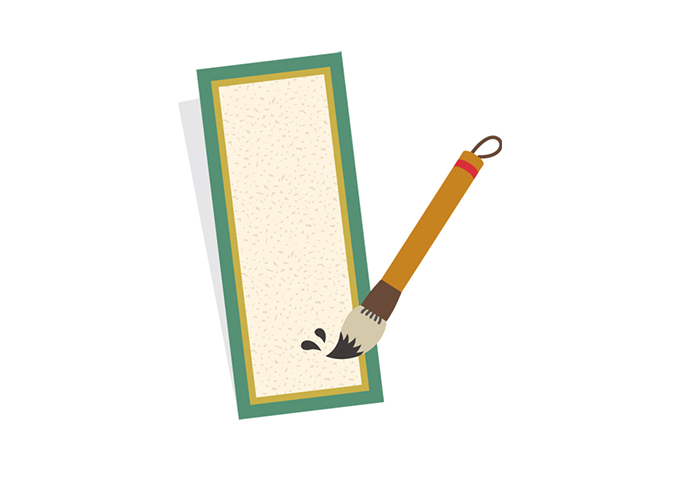
松尾芭蕉と言えば俳句、俳句と言えば5・7・5の17音で作られる日本の定型詩で、これは世界最短の定型詩でもあります。
室町時代に流行した俳諧を松尾芭蕉が芸術性を高め、単独で鑑賞に堪える句を詠んだことが俳句の元となったとされています。
近代文芸として創作性を重視して俳句を成立させたのは明治時代の正岡子規であり、俳句革新運動などを行いました。
俳句という世界で最も短い定型詩は様々な可能性を秘めているため常にさぐられていて、現在活躍している俳人も様々な流派や傾向に分かれています。
ちなみに俳句は5・7・5の17音であること、また季語(俳句などにおいて句の季節を規定する言葉)を入れることを原則としている詩ですが、どうやって作るのかも気になりますよね。
次の動画を参考にしながら俳句の作り方やルールを把握し、ぜひ俳句を作ってみましょう!
初めての俳句 キャンパス講師 No.6015 鷹俳句会・小田原
まず最初に俳句のルールは
・5・7・5の17音であること
・季語があること
だけなんですね。
季語というと難しく感じるかもしれませんが最もわかりやすいところで春と言えば「桜」、夏は「かき氷」など、その季節を感じさせる言葉が季語です。
俳句を作る場合はそもそもまず「何を詠むのか」を決めておかなければならないので、まずは俳句の材料を見つけましょう。
そんなに難しく考えることはなく、例えば目の前の自然や雨、カエルの鳴き声、夏休みでの出来事、趣味の釣りをしていること、なんでも材料になります。
そしてそれをいきなり俳句として詠むのは難しいので、材料をいつもの言葉で口に出してみましょう。
俳句の形式などは考えず、気軽に「かえるの鳴き声が聞こえてきて梅雨だなあっておもった」などで十分です。
それが終わったら改めて自分の発言を振り返り、「どれを伝えたいか」を考えて選びます。
先程のたとえならカエルの鳴き声を優先したいのか梅雨を伝えたいのかなど、選択肢も出てきますね。
そこまで終われば改めて文章を書き出し、5・7・5の音に区切る、もし言葉が合わなければ違う言い回しを考えてみるなどで調整してみましょう。
また俳句には「や・かな・けり」という切れ字を使うと俳句らしさが一気に感じられるのでおすすめですよ!
芭蕉祭の楽しみ方・みどころ3選!

次に、芭蕉祭ではどんな楽しみ方があるのか、どんな見どころがあるのかをいくつか紹介していきます。
はじめて芭蕉祭へ行ってみようと思っている方はぜひこの見どころを参考に、芭蕉祭の楽しみどころをチェックしておきましょう!
見どころ1:セレモニー
芭蕉祭の式典として行われるセレモニーは俳聖殿の前で行われ、芭蕉の遺徳を慕うたくさんの方が訪れる芭蕉祭ならではの行事です。
芭蕉祭へ行ったのならやっぱり式典は参加しておきたいもの、ぜひ見逃さないようにしておきましょう。
見どころ2:全国俳句大会
芭蕉祭の午後、献詠俳句選者等を当日の選者に迎え、芭蕉翁を偲ぶ「全国俳句大会」を開催します。
全国から集まった選りすぐりの俳句、ぜひこの機会にたくさんの俳句に触れ自分の俳句作りのきっかけにもしてくださいね。
見どころ3:史跡参観
俳聖殿の屋内に安置されている伊賀焼の芭蕉座像は芭蕉祭の日である12日のみの公開になっているなど、芭蕉にまつわる様々な像や史跡を見ることが出来る貴重な機会となっています。
ぜひこのチャンスを逃さず、芭蕉祭に合わせて開催される史跡参観などもチェックしておきましょう!
まとめ
芭蕉祭は松尾芭蕉のふるさとである三重県伊賀市で毎年芭蕉の命日である10月12日に開催される行事で、俳句好きな方にとっては魅力あふれる行事がたくさんあります。
もちろん今まで興味がなかったという方にとっても俳句の世界を知るきっかけとしておすすめできるので、ぜひ一度芭蕉祭で俳句の世界に触れてみてくださいね!